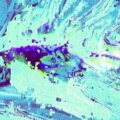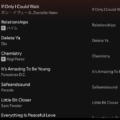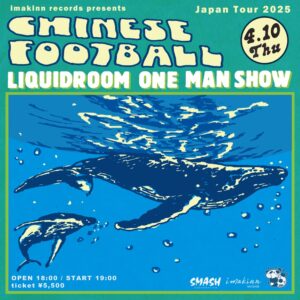NYのインディーロック・バンド Frankie Cosmos、ニューアルバム『Different Talking』を 6/27 リリース!
NYのインディーロック・バンド Frankie Cosmos、6作目にして現時点での最高傑作のニューアルバム『Different Talking』を Sub Pop から 6/27 リリース!先行シングル「Vanity」のミュージックビデオを公開。この作品は、まるで時間と空間を越えて存在しているかのようだ――まるで、私たち自身がそうであるように。記憶の断片や思い出の場所、再解釈された感情の集まりが、透明感と振動感をもったひとつの作品として形作られている。時間の流れや老いをテーマにした、しっかりとした構成のインディーロック・アルバムでありながら、鋭く“今”を感じさせるものになっている。
ボーカル・ギター・ソングライティングを担当する Greta Kline は、現代インディー音楽界で最も繊細かつ重要な作詞家の一人と長く称えられてきたが、『Different Talking』ではその歌詞が少し丸くなっている。近作を特徴づけていた皮肉なシニシズムは影を潜め、代わりに「人間の脳や心が持つ弱さ――それでも大切で不可欠なもの」への理解が現れている。
このアルバムを「原点回帰」や「過去の直接的な作風への回帰」と形容するのは失礼であり、完全に誤りである。なぜなら『Different Talking』は、「20代前半の無鉄砲さや勇気に戻ることはできない」ということを自覚しながらも、「あの頃の自分は、どこかにずっと生きている」と感じることの大切さを描いているからだ。Kline は言う。
このアルバムの多くは “大人になること”、そして “自分をどう知っていくか” に関するもの。たとえば『前に進む』ってどういうこと? 自分の過去に取り憑かれたような状態から、どうすれば抜け出せるの? 私にとって、曲を書くことがその道なんです。
Kline は10代の終わりに Bandcamp で多数の楽曲を発表し、2014年のデビュー作『Zentropy』で「NY DIYシーンの詩人」と称され、以後アメリカ・インディーシーンの中心人物となった。「若い女性が自室でシンセを手にし、数曲をネットにアップしたらスターになる」――この現在では当たり前のような成功像を、彼女はずっと前から実現し、広めてきた存在でもある。
現在の Frankie Cosmos は、Kline に加えて Alex Bailey、Katie Von Schleicher、Hugo Stanley の4人編成。Kline こそが唯一のオリジナルメンバーだが、他の3人は「共演者」というよりも「共作者」と言うべき存在だ。『Different Talking』は、外部プロデューサーを一切使わず、自分たちだけで録音・構成した初めてのアルバムである(初期のデモを除く)。
制作のため、彼らはニューヨーク州北部の一軒家に1か月半滞在。日中は制作に没頭し、夜は映画を観たり料理を作ったり、合間には抹茶を買いに町へ出かけたり。そうした日々の中で、お互いのテンポや癖を学びながら、バンドは「Kline の曲を演奏する人たち」から「1つの呼吸を持つ生き物」へと変わっていった。それが音にも表れている。Kline は語る。
10代の頃から作りたかった音の “完成形” がようやくできた気がする。リビングルームで録ったのに、スタジオと同じくらい高音質に仕上がってる。
その一体感は楽曲にも顕著だ。たとえば「Bitch Heart」では、Baileyの跳ねるようなベースが Stanley のリズムと絡み合い、「One! Gray! Hair!」では、Von Schleicher の鍵盤が Kline のメロディを美しく装飾する。歌詞はこれまででもっとも内省的だが、音楽面では最も多彩で豊か。カントリー調のギター、シンセの装飾、時に厚みのある壁のようなサウンド――豊かなテクスチャが全体を包んでいる。
リードシングル「Vanity」は、Von Schleicher が「究極のポップ・アンセム」と表現するように、完璧主義的な構成と細部へのこだわりが詰まっている。この曲は特定の対象を持たず、「Tompkins Square Park から Sunset Park まで歩きながら宇宙に語りかけるようにして書いた」と Kline は語る。「大人と子ども、支配者と被支配者、地球と草の葉、そういった間で揺れる感覚を曲に込めた。」
アルバムは「Pressed Flower」で幕を開ける。これはまるでこの作品全体の “ロゼッタ・ストーン” のような存在で、再開発と再生、時間の経過、そして「記憶が物理的な世界に宿る」ことがテーマ。懐かしさと決意が共存した曲であり、Kline の作詞の今をよく表している――「希望に満ちていながら、世界に疲れてもいる」。彼女は言う。
私はいつも、古い感情を手放しつつ、同時にそれを再び呼び起こしているんです。若い頃の自分に向き合うと、つながっている感じもするし、まるで他人のようにも感じる。
時には、過去の痛みを冗談として笑えることも癒しになる。たとえば「Wonderland」では “私のワンダーランドはちゃんと記録してる” と皮肉を込めて歌い、「Life Back」では “昨日はもう自分の人生が戻ってこないと思ってたのに、今日はそんな風に思ってたことすら忘れてる” と軽やかに解放を歌う。「Porcelain」で触れられるように、“解離” もテーマのひとつだが、一方で「Bitch Heart」では“身体が鳥肌をひいて、髪が肌にぺたっと戻るのを見てる”と、肉体感覚にフォーカスした瞬間も描かれる。Kline は言う。
歳を重ねる中で、身体への意識がどんどん高まっているんです。その瞬間をちゃんと感じ取りたいと思うようになった。
ラスト曲「Pothole」は、軽やかで皮肉っぽく、エゴを打ち砕くようなユーモアに満ちている。そして最後には「ここは夕焼けだけど、そっちはどう?どうやったら空をピンクにできたの?」と問いかける。この余韻こそが、Frankie Cosmos らしい曖昧で希望に満ちた締めくくりだ。Kline は言う。
世界はただ在るもの。私たちはその中に意味を見出さなきゃいけない。意味が向こうからやってくるのを待つんじゃなくてね。世界は大きくて、美しいかもしれない――だからこそ、問いを立ててみよう。